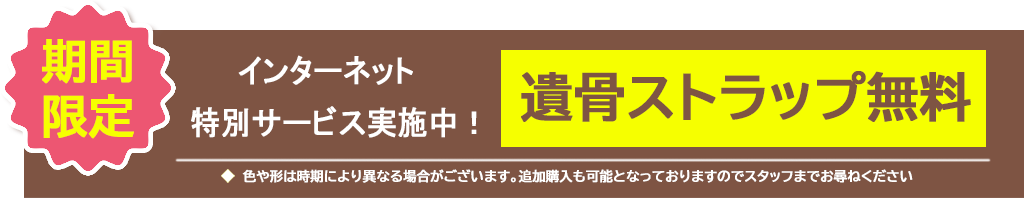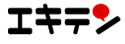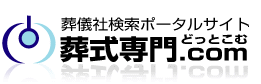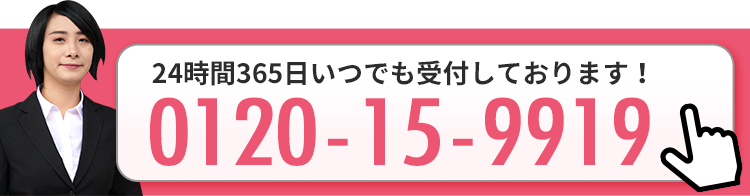昨今、ペット=家族と言った関係性が深まる中で、ペットのとのお別れも人に近しい形で執り行いたいと願う人が増えております。
そうしたニーズに応えるべく生まれたのが
ペット火葬
と呼ばれるペット専門の火葬社となります。
今までは各市区町村毎にある市営の火葬場の一部にペットの火葬も行うことが出来る施設が稀にある程度でしたが、こうした施設の場合には費用は安くとも1日の予約数が2~3件程度でとてもではないですが、ご希望されていらっしゃる全ての飼い主様にサービスを提供することが難しく、忙しい時期の場合には1週間~10日先まで予約がいっぱいになってしまっているということもございました。
さらに、市営のペット火葬の場合には遺骨のお返しのない合同葬が殆どとなり、遺骨のお返しがある場合でも飼い主様が収骨を行えない場合も多くございます。
こうした理由から昨今では飼い主様ご自身がご自宅で長期間ペットの安置が難しいことや、なによりも
ペットの収骨を人と同じように自分たちで行いたい
と言った理由から
民間のペット火葬社
が注目を集めております。
この民間のペット火葬社にはさらに大きく分けて2つ種類があり
・移動火葬車両を利用した出張専門のペット火葬社
の2つの種類のペット火葬社の種類の中からご希望に合ったペット火葬社をお選びいただく形となりますが
どちらの場合でも飼い主様がペットの遺骨の収骨を行うことが出来るプランがある
と言った特徴がございます。
そのため、ペットの遺骨の収骨を確実に行いたい場合には民間のペット火葬社に依頼する形になることがほとんどとなります。
そして、そんな収骨ですが
ペットの収骨の方法は人と異なるのか?
と疑問に思う方も多くいらっしゃるかと思います。
その中でも特に
喉仏
については謎に思われる方も多くいらっしゃり、人の場合には喉仏を重視する文化がありますが
そもそもペットに喉仏があるのか?
と言った点でペットの喉仏の収骨について謎に思われる方が多くいらっしゃいます。
今回はそんな
意外と知らない喉仏とペットの収骨について
ご紹介させていただきます。

まず初めに喉仏と聞いて真っ先に思いつくのが
男性の喉元にあるポッコリ飛び出した部分
と言ったイメージが一般的になるかと思います。
そして、人の場合にも収骨の際に
喉仏
を重視する文化があることから、この男性の喉元にある一般的に目で見て分かる喉仏を
喉仏=男性の喉元にある骨
と言った認識をされていらっしゃる方も多くあるかと思います。
しかし、ここで生まれてくる矛盾として
人の火葬の際には男性にも女性にも喉仏がある
と言ったところです。
では、この喉仏とは実際どのような物なのでしょうか?
まず男性の喉元にある突起状になって目で見て分かるこの喉仏というものは実は
骨ではなく軟骨
になります。
そのため、火葬を行った際にはこの男性の喉仏と言われる部分は実は焼けてなくなってしまいます。
また、骨ではないのならこの喉仏というものは一体何なのか?と言った疑問があるかと思いますがこの男性の喉元に見える喉仏というものは
喉頭隆起と呼ばれる喉の真ん中辺りにある甲状軟骨が隆起したところ
となり、男性の声変わりの原因はこの甲状軟骨が大人になるにつれて発達するため声変わりが起こる形となります。
また、この甲状軟骨が発達をしないだけであってこの喉頭隆起といった部分は女性にも存在します。
では、この喉頭隆起と言った部分が喉仏という部分になるのか?というとそうではありません。
喉頭隆起は先に申し上げた通り甲状軟骨という軟骨にあたる部分になり、軟骨は骨とは違い火葬を行った際には燃え尽きてしまう部分になるため、この外から見て分かる一般的な喉仏は残りません。
では、喉仏はどこになるのか?
収骨の際に重要視される喉仏とは
首の上から二番目にある第二頸椎(軸椎)
の部分が実は喉仏の部分となります。
この
第二頸椎が収骨の際に喉仏と称される部分
となり日本では
仏さまが座禅を組んでいらっしゃる姿に似ている
と言った形で語り継がれており、現在ではあまり耳にしない迷信となりますが
喉仏が綺麗に残っていた=生前に善行を行っていたから
とされており、こうした善行を重ねた人間は
極楽浄土へ行くことが出来る
とされていたため
喉仏が綺麗に残る=極楽浄土へ行くことが決まっている
と言った考え方が信じられており、そのため喉仏が綺麗に残ることは良いこととされ、また収骨の際に喉仏の部分を注視する文化が生まれたとされております。
このように、喉仏には仏教的な考え方が非常に強く表れており、宗教的な観点がかなり薄まりつつある昨今でも知らず知らずのうちに習慣化し、日本の大切な習慣となっている喉仏ですが、ではペットの場合はどうでしょうか?
続きまして、ペットの喉仏について詳しくご説明させていただきます。

ペットの火葬を執り行わせていただいている際によくご質問いただくことが
人の場合には喉仏があるけれどもペットには喉仏があるのか?
と言った内容になります。
この喉仏というものは先にもご説明させていただいた通り
第二頸椎(軸椎)
となるため、体の中で頸椎とされる骨がある生き物であれば基本的にどの生き物にも存在します。
ただし、個体の大きさによっては目で見ることが難しい部分となります。
例えば
犬、猫、うさぎ等
お体の体重が1kg以上あるような動物の場合には比較的目で見て喉仏がどこにあるのかが分かりやすいとされております。
ただし、犬や猫などの生き物の場合には4足歩行であること等から
喉仏が人よりも細長く前も後ろも突起が目立つ形
をしております。
ですが、仏様のような形と言った点では似たような形をしているという特徴もございます。
そのためペット火葬社の多くが
首の上から二番目のお骨を喉仏
としてペットの場合でも収骨の際にご説明していることがほとんどとなります。
ただし、先にお伝えした通り体の大きさが1kgに満たないハムスターや小鳥、デグーなどの小型の生き物の場合にはお骨全体がとても小さく、さらに、頸椎部分はさらに小さなお骨で形成されている個体も多いため目で見て判断することは困難とされております。
そのため、小動物の収骨の際にはこの喉仏の説明が無いことがほとんどとなります。
ただし、頸椎がある生き物であれば上から二番目の第二頸椎が喉仏にあたるため、もしこうした喉仏を大切にされる習慣のある方の場合にはお探しいただくのも良いかと思います。
また、人の火葬でもペットの火葬の場合でも問題視される
遺骨の残り方
について、特に
喉仏が綺麗に残っていることが当たり前
のように感じていらっしゃる方も多いかもしれませんが
遺骨の残り方はお体の状態やお骨の状態によってかなり左右される
ため、遺骨の残り方は千差万別となります。
そのため、喉仏が綺麗に残っていない場合も多くございます。
例えば
骨粗しょう症
などはお骨が綺麗に残らない原因となりやすい病気となります。
こちらは、お骨がスカスカになってしまう病気となりこうした骨にまつわる病気をお持ちの場合には、一部の骨だけではなくお体全体のお骨が比較的崩れやすくなってしまう傾向がございます。
特にこうした骨粗しょう症を引き起こしてしまう病気の中に
腎臓病
があり、高齢の犬や猫がかなりの割合でかかってしまう高齢病としても認知度の高い病気となります。
そのため、腎臓病を患ってしまっているペットの多くが骨粗しょう症も合併症として患ってしまっており、お骨が割れやすいという特徴がございます。
そのため、高齢のペットの場合には比較的骨が崩れやすいペットが多い傾向があるのはこのためだと思って頂いても良いかと思います。
ですので、必ずしも全身の骨が全て綺麗に残ることが当たり前ではないことを念頭に入れておくことで、遺骨の残り方を見た際のショックが少なくなることや、なによりも最後までペットが一生懸命に生きていたのだなということをご実感いただけるかと思います。
また、最後にペットの遺骨を収骨する際の収骨方法と知っておくと便利なワンポイントをご説明させていただきます。

ペットのお骨上げについても基本的には人と同じ形で収骨をすることが一般的になります。
そのため
の順に遺骨を納めていただく形が一般的になるかと思いますが、ペットの場合には4つ足の生き物がほとんどとなるため、先に前足と後ろ足を納めるというペット火葬社もあります。
また、ペットと人で異なる点ですと
人の場合とは違い2人1組での箸渡しでの収骨をほとんどしない
と言った点になります。
理由としては
ペットの場合には人よりも骨が小さい
と言った点と
骨粗しょう症のペットはかなり遺骨が脆い
と言った2つの理由から、一般的にペットの場合には遺骨を綺麗に残すために箸渡しはしないと言ったことが多くございます。
ただし、日本古来の風習・習慣を大切にされるペット火葬社や飼い主様の場合には箸渡しをする場合もございます。
ですが、その際にはお互いの掴む強さや骨壺へ運ぶ際の早さなどを人よりも気にしてあげないとお骨が崩れてしまう可能性が非常に高いため注意をした方が良いでしょう。
また、人の場合と異なる点で
箸渡しをしないことがほとんどとなるため収骨用の箸が人の物とは異なる場合がある
と言った点になります。
人のような異なる箸を2つ用意するのではなく、同じお箸を用意している場合や、そもそもお箸の数が複数本ある場合、または、ペットの種類や小さなお子様や外国の方でも収骨がしやすいようにトングを用意しているペット火葬社もあります。
そのため、どちらかと言えば収骨がしやすいように使い勝手の良い箸が用意されている場合も多くあるため、箸を使うことが苦手な方でも収骨がしやすくなるような工夫がされていることも多くございます。
また、収骨の際に一番気を付けるべきところが
頭蓋骨
となり、この頭蓋骨の収骨は人の場合とは違いなるべく綺麗な形を保ったまま収骨をしてあげたいと言った方の方が多くいらっしゃいます。
しかし、どのようにしたら頭蓋骨を綺麗に収骨できるのか?
こちらについてはまず
下顎を先に骨壺に出来る限り納める
という形を取ると良いでしょう。
どうしても下顎と頭蓋骨(上顎)の部分は軟骨等で繋がっているため、火葬をした際には上下が分かれてしまう部分となります。
また、下顎はさらに中心から左右に分かれるような形がほとんどなります。
そのため、下顎ごと頭蓋骨全体を持ってしまうような形を取るとお骨が落下してしまう可能性が非常に高くなり、それを防止するために強く持ってしまうと今度は頭蓋骨が崩れてしまう可能性があります。
ですので頭蓋骨の収骨の際には出来る限り頭蓋骨と下顎を別にしてから収骨をすると良いでしょう。
また
頭蓋骨を持ち上げる際に口を持つのはNG
となります。
なぜなら、ペットの場合には歯磨きが苦手な種類が多くそのため歯周病等と歯の病気になってしまっている個体が多く、歯周病が原因となり歯や顎が脆くなっている個体がほとんどとなります。
そのため、口の辺りがかなり崩れやすく口元を持とうとすると頭の後ろの重みや箸の圧に耐えきれず崩れてしまうことが多くございます。
さらに
後頭部を持つことも避けた方が良い
とされております。
理由としては後頭部の骨が薄い部分となっているのはもちろんの事、後頭部を持ってしまうとお顔の前後のバランスが取りにくくなってしまうため、落下してしまうリスクがあるからです。
ですので、頭蓋骨の収骨を行う際には
両目の目頭から箸を後頭部方向へ入れそっと摘まみ持ち上げる
と言った形が一番バランスが良く、また骨が頭蓋骨の中では比較的密度のしっかりとしている部分となるため、骨が崩れてしまうリスクを出来る限り減らした状態で頭蓋骨の収骨を行うことが出来ます。
また、頭蓋骨の収骨をした後に
喉仏
を納めていただく形となりますが
喉仏やその他のお骨の形の関係から上手に骨壺に納めることがむずいかしい可能性がある
ため、無理に仏様の方向を上向きにしようと骨壺の中に何度もお箸を入れたりせず、一番納まりのよい形で納めてあげることが遺骨を傷つけるリスクを最大限まで減らすことが出来ます。
以上がペットの遺骨の収骨をする際のワンポイントとなります。

いかがでしょうか?
喉仏という存在がどういった物かいまいちよく分からないけれども、仏様のような恰好をしていて、とにかく収骨の時に一番最後に入れる大切な部分!と思っていらっしゃった方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
現在ではかなり宗教的な考え方が薄れており、宗教的な考え方を度外視した習慣だけが残っていると言った部分も強く表れてしまっております。
だからこそ、改めてなぜこうした風習があるのかを知ることでより故人を思う昔の人々の想いを知ることが出来ると共に、意味を知ることでより一層大切なペットさんへの思いも深まるかと思います。
記事担当 阿部
・ペットが亡くなったら?これだけ覚えていれば安心!3つのポイント
・立会でのペット火葬を行った際にペットの遺骨はどのくらい拾うものか?~ペット火葬の豆知識~
店舗名 ペット火葬真愛メモリアル
所在地
埼玉支店
〒333-0845 埼玉県川口市上青木西4-23-23 ピュア上青木西102
東京支店
〒160-0022 東京都新宿区五丁目18-20 ルックハイツ新宿803
横浜支店
〒231-0063 神奈川県横浜市中区花咲町1丁目48-3 ロゼ桜木町 406
フリ ーダイヤル 0120-15-9919
営業時間 24時間365日
ホームページURL
https://saitama-pet-memorial.com/